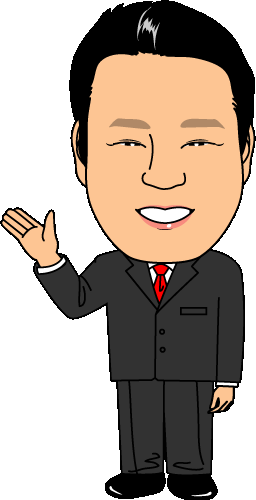スタッフのおすすめ
- 顧客のど真ん中を知る

工藤 正悟現代日本の階級構造
早稲田大学の橋本健二教授が発表した論文
- 資本家階級(4.1%)
大部分が小零細企業の経営者、資産総額は4,863万円。 - 新中間階級(20.6%)
公務員と上場企業管理職、家計資産の平均額は2353万円。 - 旧中間階級(12.9%)
自営業、家計資産は2917万円。 - 正規労働者(35.1%)
資産総額は1428万円。 - アンダークラス(14.9%)
資産総額は1119 万円。
顧客のど真ん中を知ることで、誰に商品を届けるのか具体的にイメージできる。
- 資本家階級(4.1%)
- やっておけばよかったをなくす

江原 智恵子人はやったことを後悔するより、やらなかったことを後悔する方が強いそうです。後になってやっておけばよかったと思うならば、思った時にやっておくことが大事です。やらなかったことの方がずっと後悔するわけですから、やったことは無駄でも損でもなく、むしろ経験として残るので、やった方がよいと思います。
忙しい時などは特に後回しにしてしまいがちですが、一日一日平等に齢をとっていて、限りある人生ですから、思った時にやらないと後悔します。
全く後悔のない人生なんてないと思いますが、なるべく後悔を少なくするためには思った時に行動するくせをつけておくと良いと思います。
- 一心(イッシン)になる

土肥 宏行禅についての住職さんの言葉です。
禅とは心についた嬉しい、悲しい、苦しいといった気持をほどく方法を教えてくれるものだそうです。
よく座禅を組むと無心になれるのかと言われるが、無心=なにも考えないではなく「一心になる」ということです。一心とは今やっていることに対して集中し、心も体も完全に1つになっている状態。他の言葉だと「初心に還る」になるのかと思います。仕事などで「さあやるぞ」と思った心には雑念がありません。
「人からうまくよく見られたい」とか、「なぜこんなことをしなければならない」といった後から付くものが雑念です。
雑念のない「素直な心」が初心です。寺の修行では、徹底的に叱られるのだそうです。
自分というものを否定し、「自分が」という心の固まりをほどくことでぶれない心を養うことができるということです。
- 人は外の世界を見ているようで、実は自分自身を見ている。

中澤 正裕相手の言動に対して、「優しい人だな」「なんだか話しづらいな」と、さまざまな印象を持ちます。その印象の一部は相手そのものではなく、自分の心が映し出されているといいます。心に余裕がないときほど、相手の少しの言葉が強く聞こえ、逆に気持ちが落ち着いていると、同じ言葉でも自然と前向きに受け止めます。
相手の態度が気になるとき、それは相手の性格ではなく、自分の疲れや焦り、または先入観が影響している場合もあります。そんなときに、「この感じ方は本当に相手のせいなのか?それとも自分の心の状態なのか?」と一度立ち止まりましょう。
「良いものへの気づきもまた自分自身を映している」という考え方があります。誰かの丁寧な仕事ぶりに感心するのは、自分の中にも丁寧さを大切にしたい思いがあるからですし、誰かの気配りや優しい言葉に心が動くのは、自分自身もそうありたいと願っているからです。この人のここがすごいと感じる瞬間は、自分にもその素質が種として存在している証拠です。人と接する中で、「これは自分のどんな部分が映っているんだろう?」と少し意識してみると、新しい気づきが得られるかもしれません。
- 価格は誰が決めるのか?

堺 友樹モノの価格は、例えばお寿司屋だと『時価』とかあったり、あるチェーン居酒屋のように全商品均一価格だったりしますが、お客が価格を決めるモノもあります。
静岡駅前の百貨店にある水族館は、土日は料金が設定されていますが、平日はお客が最後に料金を決めて支払いをします。
これをポストプライシングというそうです。
それでは誰も払わないだろうと私は思っていたのですが、1,500円を払う人もいてびっくりしました。自社での商品に対して、お客がいくら出すだろうと考えてみるのも良いかもしれません。
- ハラスメントについて

中澤 正裕最近では、ニュースや職場でも「また新しい○○ハラが出てきた」と話題になります。
パワハラ、セクハラに加えて、マタハラ、スメハラ、エイジハラ…。企業としては「どこまで配慮すればいいのか」「これもアウト?」と、線引きに悩むことも多いと思います。
では、なぜこんなにも“ハラスメント”が注目されるようになったのか。それは、誰もが自分の感じ方を持ち、それが尊重されるべきだという価値観に変わってきているから。
“ハラスメント対策”というと、とても堅苦しく聞こえるかもしれません。
でも本質は、「誰もが安心して働ける場所を作る」という、すごく当たり前で、人間的なことです。
- 賢者は何者からも学び、愚者は何者からも学ばない

丹下 優子古典より。ある位の高い人物が、位の低い人の行いにも注目し、善いことであれば素直に取り入れた、という話から。
著名な人や世の中で凄いと言われている人の話は受け入れても、自分がそうでないと感じている人の話は頭から否定する、という現象は、日常でも少なくないように思う。
「賢者は何者からも学び、愚者は何者からも学ばない」
誰が言ったことでもどんな状況でも、善い事であることに変わりがなければ、誰のためにでもなく、素直に受け入れられる姿勢を持ち合わせていたいと思う。
- 思い込みが現実を変える

中瀬 拓哉世界No.1コーチと呼ばれているアンソニー・ロビンズ氏の言葉で、「人を動かすのは現実ではなく、その人の“思い込み”である」というものがあります。
仕事の中で、「これは難しい」「時間がない」「自分には向いていない」と感じることがあるかもしれませんが、それは本当に“現実”ではなく、自分の中の“思い込み”がそう感じさせていることが多いようです。
ロビンズ氏のセミナーでは、「火の上を裸足で歩く」という体験があります。
ほとんどの人が「無理だ」と思いますが、「できる」と信じて一歩踏み出した人は、本当に火傷せずに歩き切るそうです。これをする目的は火を歩くことではなく、限界を決めているのは“自分の思い込み”だと気付いてもらうためです。
仕事でも、「お客様は聞いてくれない」「うちの業界では難しい」と思った瞬間、行動が止まります。でも「もしかしたらできる」「一度試してみよう」と考えれば、可能性は一気に広がると思います。
- 「譲る」ことが無条件な善ではない。

丹下 優子側道から交通量の多い道路に進入したい車がある時、優先道路を通行している車は、前を譲ってあげることはよくあることだ。しかし何台も何度も譲るなど、その度を越してしまうと、本来の円滑な交通の流れを妨げてしまうことになる。
日常や仕事においても、もちろん「譲る」という行為は善い行いであるが、自己満足や保身になっていないか、常に自分の役割や全体への影響を考慮することを忘れないようにしたい。
- 「善き言葉」と「行い」は歴史に残る

中瀬 拓哉先日、豊洲で開催されていたラムセス大王展というものに行ってきました。
エジプト史上「最も偉大な王」と呼ばれているエジプトのファラオがラムセス2世という人物だそうです。彼は戦士であり偉大な建築家でもあったそうです。
その時代の古代の知恵の書には「善き言葉は永遠に残る」と記されています。
また、「人は富ではなく、行いによって評価される」という教えもあります。現代は成果や数字で評価されがちですが、結局のところ、人の記憶に残るのはその人の行動や周りへの影響力だと思います。僕も日々の仕事や人との関わりの中で、小さな 「善き言葉」や「行い」を積み重ねていくことで、関わった人の心に残る何かを作ることにつなげて行きたいと思いました。
- 改善と改革と時間の使い方

工藤 正悟改善とは、日々の仕事の小さなことを少しずつ良くしていく活動であり、改革とはビジネスのコアな部分を変えることである。
効果の面で見ると、改善はモチベーションに繋がるが、本質に関わる改善以外は継続しないと言われている。また、本質に関わる改善も大きな効果は発揮しない。一方、改革は大きな効果を発揮するが道筋が見えづらく、時間と手間がかかる。
改善にたくさん時間を使っても効果が少ないので、改善は良さそうであればサクッと決めて動く。
改革はそもそも時間がかかる、じっくり考えて行うべき。
今、自分が何に時間をかけているか考えて動いたほうが良い
時間をかけてるから良いのではなく、良いことに時間をかけるべきである。
- ネガティブ思考はエネルギーになる

江原 智恵子自分の目標を紙に書けと言われてもなかなか思い浮かばないときは、ネガティブな側面から考えてみるとよいそうです。
自分の人生において絶対に欲しくないもの、起こって欲しくないことなどネガティブなことを全て書き出してみると、自分の奥にある真の目標が発見できるかもしれません。
欲しくないものがはっきりすれば、後はそれと反対の事をすればいい訳ですから目標をもちやすくなると思います。
- 商品を絞る

土肥 宏行山形県にある加茂水族館。
イルカもペンギンもいないメインの展示生物はクラゲといった尖った水族館です。この水族館、もともと特徴がのなさから年々来館者数が減り続け、存続の危機に陥っていました。そんな時たまたま珊瑚の水槽から湧いて出たクラゲにお客さんが盛り上がっていることをヒントにメインの展示生物をクラゲに絞り、これが見事に当たったようです。
ただ展示生物を絞ったからといって楽になったわけではない。
クラゲの平均寿命は4ヶ月で、水質維持と固体の入替えはとても大変で、大手水族館は真似ができない。加茂水族館は商品を絞り、大変なことに正面から向かい合い磨き続けたことにより、それが尖った個性となって受け入れられているという話でした。
- 何を伝えるではなく、何を伝えないかを考える

土肥 宏行アップルのiMacの30秒のCMに5つのメッセージを盛り込むことをスティーブジョブズが提案した時に、リークロウとの間のやり取りです。
リーはメモ帳から5枚の紙をちぎると、1枚ずつ丸めはじめ
「スティーブ、キャッチしてくれ」と言い、紙の玉を1つ投げました。
スティーブは難なくキャッチして、投げ返しました。「これが良い広告だ」
「またキャッチしてくれ」と言って、今度は紙の玉5つ全てをスティーブのほうに投げました。スティーブは1つもキャッチできず、紙の玉はテーブルや床に落ちました。「これが悪い広告だよ」
メッセージはまず受け取ってもらわなければ話になりません。ついあれもこれもと言いたくなりますが、何を伝えるかでなく、何を伝えないかについても考えることが重要です。
- 負ける要因は3つ

堺 友樹林修氏によると、勝つことには偶然があるが、負けることには大きく3つの共通点があるよう。
1つ目は【情報】。
情報が多ければ勝負する前に勝ち負けの判断をすることができる。残りはこれでよいという【思い込み】と自分はできるという【慢心】だそう。
事業においても同じで、業績が良くてもこのままでよいという思い込みをせず、慢心した心持ちにならず、世の中の情報にアンテナを立てて感じ取る必要がある。これは社長のみならず社員にも必要なことではないかと思う。
- 完璧を目指すより、まず終わらせろ ??

中澤 正裕「考えるよりもまず行動」に似ていますね。とにかくスピードが大事。
完璧を待っていたら、機会を逃してしまう。今の時代に合っている考え方です。
よく出てくるワードですが、果たして本当にそれが正解なのか。と、ふと考えました。結局は、「完璧」と「まずやる」のバランスが大事だということです。
スピード重視の時には、「何を捨て、何を守るか」の見極めが大事です。
「優先順位を間違えるな」というメッセージとして受け取るべきではないでしょうか。
- 気にしたり気にされたりを大切にしよう。

丹下 優子ラジオで聞いたある女性の話。コロナでリモート勤務や時差通勤になり、数ヶ月ぶりにコロナ前の時間帯の電車に乗った時、突然ひとりの女性から声をかけられたそうだ。
「お元気だったんですね!安心しました。お見かけしなくなって心配してたんですよ!」その女性はいつも同じ電車に乗り合わせる方で、顔は知ってるけどもちろん話したことなどない女性だった。気にかけてくれていたことが嬉しくで、話をしながら2人で人目もはばからず泣いてしまったそうだ。なんだかほっこりする話だ。
誰かの何気ない一言で、今日一日頑張れることがある。おかしなことも多い昨今だが、ご時世を悲観するばかりでなく、気にしたり気にされたりすることを嬉しく思える感性は持っていたいと思った。
- 苦は楽の種 楽は苦の種

中瀬 拓哉私が通っていた小学校の音楽教室の壁に飾ってあった言葉だ。
当時は何のことやらと思っていたが、時間が経つと意味が分かり、この言葉がずっと頭の片隅にある。
読んで字のごとくだが、「面倒だな・・・」とか、「なんで自分が・・・」とか「苦労」を今の内にやっておくと後々自分のために繋がるというもの。逆に「とりあえず後回しにしよう」とか「やらないでおこう」とか今「楽」を選択すると後に何であの時やらなかったのだろうと後悔し、自分に返ってくるというもの。
今後も仕事でもプライベートでも、「苦は楽の種」という考えを持って取り組んでいこうと思った。
- 扱い方の教科書

工藤 正悟ホストの営業方法で紹介されていました。
初めてくる客は、そのホストをどう扱っていいか分からないから、こちらから使い方を示す必要があります。
かっこよく見られたい→かっこいい人と扱われている所を見せる
打ち解けやすい印象を与える→ボケて周りから突っ込まれる
周りがそのホストをどう扱っているかを見て、その人にどう接すれば良いかを決める、それが日本人にとっての教科書になるようです。
周りがすごいと言ったらすごい人として扱ってもらえる(本心は分からないけど)
相手が求めているキャラクターになり振る舞う、これも一つのコミュニケーション力
- 身をもって実行する人になる

江原 智恵子「もっともらしいことを言う人」がいますが、言っているだけの人、いわゆる口だけの人は共感することができません。
逆に口数が少なくても身をもって正しいことを行い、努力をしている人は尊敬することができます。
口だけでなく、自らの手と足を使って実行することが大事なのだと思います。その姿をまわりがみて、その人への信頼感や尊敬が生まれるのではないでしょうか?
日々の自分の言動と行動を振り返って、身をもって実行するということを少し意識してみてはいかがでしょうか?
- 潜在意識をプラスにする

江原 智恵子人の心には自分で意識できている顕在意識と意識できていない潜在意識があり、潜在意識は人の心の90%以上を占めています。
潜在意識の特徴は、「潜在意識にインプットしたものが自分の人生に実現してくる」ということです。潜在意識は善悪の判断ができないので、良いものを入れればよい人生になるし、悪いものを入れれば悪い人生になってしまいます。
自分が思っていることが潜在意識にインプットされて自分の人生として実現するのであれば、潜在意識にプラスのイメージを増やして、実現したい事を強く思ったり、口に出して言ったり、行動することで自分の人生が良い方向に変わっていくのではないかと思います。
- 「希少性」という魔法

土肥 宏行ある大学の講義の話です満腹の大学生にカレーを売るとしたら何と言って売りますか?というテーマでした。
ランチも終わってお腹がすいていない大学生の前にカレーを差し出して「食べたい人」と聞きます。誰も手をあげません。
そこで講師の方が言います。
「ある情報をあなた達に伝えることによって、きっとこのカレーを食べたくなりますよ」と言います。
学生たちはとても気になります。
そこにカレーを作ったという鈴木さんという女性がゲストとして出てきます。
講師は「この方は鈴木一郎のお母さんです。そしてこのカレーはイチローが毎日食べているカレーです」そのあと改めて「このカレーを食べたい人」と聞くと皆手をあげたという話です。女性が出てくる前と後ではカレーは全く変わっていません。でもそのカレーが欲しくなったのは人が本能的に手に入らないものを欲しがるという心理が働いたのです。
どこにでも手に入るものは欲しくない。いつ手に入るかわからないからこそ希少なものになって欲しくなる。
- 既存の考え方を捨てる

堺 友樹あるテレビ番組で、コンクリートのコーティングを行う会社が紹介されていました。
従来の色付きコーティングではなくスケルトン工法という手法を用い、コンクリートのひび割れ等を見える化する方法を用い、橋梁やトンネルのコンクリートにコーティングする会社です。
きっかけは、顧客から3年前にコーティングしたコンクリートが破損しているので直してほしいと連絡があり、その時、これは普通のことではないのではないかと考えたそうです。
このように、今の現状起きていることを普通ではないと感じることが大切なのではないかと感じます。
仕事においてもそうです。
今までのやり方が定着すると、それが一番良い方法だと感じます。しかし、外から見たら、その方法は普通ではないかもしれません。
今一度、既存の考え方を捨て、新たなより良い方法を模索してみるのも良いと思います。
- 雨晴れて傘忘れる

中澤 正裕雨が降っていたときには大切にしていた傘も、天気が晴れたとたんにその存在を忘れてしまう――そんな人間の油断しやすさ、忘れやすさを表した言葉です。
人間は「危機」や「困難」に直面しているときは、注意深く、慎重になります。ところが、一度その問題が解決すると、気がゆるみ、自然と意識が薄れていきます。トラブル直後にはチェック体制を強化したり、報連相を徹底したりと、対策をとります。何事も起こらないと、「もう大丈夫だろう」と判断して、以前の状態に戻ってしまいます。脳科学的にも、「危機を忘れるようにできている」そうです。不安やストレスを感じ続けると脳が疲弊するため、時間がたつと自然と記憶が薄れていく、脳の防衛反応なんだそうです。
「うまくいっている今こそ気を引き締める」、「何も起きていないときにこそ備える」仕事の質を保つ上で欠かせない姿勢です。
毎日の点検、確認作業、地道なことほど、「慣れ」が入ると省略したくなるものです。あえて意識を向け、「晴れていても傘を持ち歩く」ような心構えを持ちたいですね。
- 『後悔最小化理論』で選択する

丹下 優子年を重ねると、もっと冒険すればよかった、挑戦しておけばよかった、などと“しなかった後悔”をすることが多くなるそうだ。実際に行動したけど失敗してしまったことは、心理的免疫システムが働いて忘れられるが、しなかった後悔は薄れることは少ない。
まったく悔いのない人生なんてないだろうが、10年後20年後振り返った時、後悔が最小となる選択はどっちだろう?という視点で判断すると良いかもしれない。
自分とは『これまでの選択の結果』である、ということも常に意識しておきたい。
- 明日やろうはバカやろう

中瀬 拓哉2007年に放送されたドラマ「プロポーズ大作戦」をご存知でしょうか?
そのドラマの中で主人公に対して発せられたセリフです。
当時10歳でしたが、この言葉が今でも記憶に残っています。
5分10分あればできるちょっとした仕事や、期限が少し先の余裕のある仕事等が出てきた時、つい明日に回そうと考えてしまうこともあるかと思います。しかし、明日に回すと明日にはまた明日の仕事が出てきて、結局後回しになる。なんてことがあります。
そんな時私は、明日やろうはバカやろうの精神で、手元にある仕事は今やる今日やるの考えでどんどんと終わらせられるおように意識しています。
- 現代的宗教観

工藤 正悟現代では3つの宗教観がある。
- 人間至上主義
自身の内面に真実の答えがあり、その答えは尊いもので他人と違っても問題がないものである→多様性の表れ - 資本主義
経済的に優れることが絶対的な正解と捉えることである。常に進歩を求め、怠惰を許さない - データ至上主義
人間至上主義に反する考え方。データで表されるものを正しいとし、合理的な答えこそが正解である。
これまでの宗教観は神がいて、どのように生きれば天国へ行けるか示すものであったが、現代の宗教観はどのように豊かに生きるかに比重が置かれている。
どの宗教観が正しいと言うものではないが、自分の考えが偏っていないか俯瞰的に見る目安となる。
- 人間至上主義
- 全ては天からの「借り物」と感謝する

江原 智恵子お金もパートナーも子供も、この世には自分のものと言えるようなものは実は一つもないそうです。
自分の肉体でさえ天からの借り物で自分のものではないと考えると、パートナーや子供を自分の所有物のように扱ったり、束縛してはいけません。
パートナーなら、子供なら、こうしてくれて当然などと相手の意思や時間を奪わないようにしたいものです。
人は「自分のもの」と信じ込んでいたものを失った時に大きなショックを受けます。
「自分のもの」という思い込みや執着心から解放されれば穏やかな心でいることができます。
又、生きていくうえで心がぐっと軽くなり幸福感も増すのではないでしょうか?
- 自分の中のジャイアニズムを考える

土肥 宏行「お前のものは俺のもの。俺のものも俺のもの」。
ドラえもんのジャイアンの有名な言葉ですが、なんとも独裁的で自分勝手な言葉ですよね。
「正しいのはいつも俺だから、自分の考えは誰もが納得する」と思っているからでしょう。
この周囲の人は自分と同じ考えを持ち、同じように判断するという考えをフォールスコンセンサス(誤った 意見の一致)というようです。
この過度のフォールスコンセンサスは他人の気持ちを狭い範疇でしか考えられなくしてしまいます。ジャイアンはのび太と彼なりに友達でいようと思っているようです。
ジャイアンの誘いをのび太が断ると怒ったりするわけです。
なぜ自分と同じように考えないんだと。誰もが少なからず自分が正しいと思って行動しているともいますが、相手も必ずしも同じ考えだと思いこまない方が良いのでしょう。
- 仕事はベースボール

堺 友樹サラリーマン金太郎という漫画に出てくるフレーズです。
主人公の矢島金太郎が公共工事の受注を行うにあたり、会社では誰もその仕事をしたくなく、設計の部署と衝突してしまいます。
そんな中、設計のある社員が『君は一人で仕事をしようとしている。仕事はベースボールと同じでチームで行うものだ。会社を一つのチームにまとめ上げろ』とアドバイスしました。仕事は一人で完結するものはありません。必ず自社の誰かが関わっています。仕事に対する意識が変化していくこととなります。
- 感覚と違う確率

中澤 正裕勝率55%を誇るAさんは10万円を持ってカジノに行き、買ったら1万円、負けたらマイナス1万円のゲームをします。
倍の20万円になるか、ゼロになるか、いずれかの状況になるまで継続します。
この時、ゼロになる可能性は・・・約12%です。勝率45%のBさんも同じ状況でカジノに行きます。
この時ゼロになる可能性は約88%です。どちらも大体半分くらいの勝率ですが、ゼロになる確率では大きな差が生まれます。
この確率が仕事に通じるものがあるか分かりませんが、長期間にわたり継続して行うことについては1つ1つの正確性、成功確率が大きな差を生むのだろうと思います。
- 今いる人の今ある力で最大の成果を

丹下 優子タレントの坂上忍さんは、「雇った人は終身雇用、その人の退職金を出すために仕事をがんばっている」と言っていました。
30年近く担当しているマネージャーには一度もダメ出しをしたことがないそうです。それは、今いる人の今ある能力と自分とでできることをやればいいから、という考えに基づいているようです。
時にはダメ出しも必要だと思いますし、終身雇用がいいとか社員は大切にしようとか言いたい訳ではなく、ただとても自然でストレスフリーな考えだなと感銘を受けました。もっとこうだったらな、と周りに不平を持ちがちですが、これくらいの潔さを持つことが処世術のひとつなのかもしれません。
- 制約に集中することの重要性

中瀬 拓哉1984年に出版された 『ザ・ゴール』 にある考え方です。
『ザ・ゴール』は、一見うまくいっていない工場が 「制約理論」 を使って劇的に改善するストーリーです。ここでのポイントは、「全ての工程を均等に効率化するのではなく、ボトルネック、つまり最も生産の流れを妨げている部分に集中して改善すること」です。
たとえば、工場の生産ラインに 1台だけ極端に処理が遅い機械 があるとしましょう。他の機械の処理能力をどれだけ上げても、この遅い機械がボトルネックとなり、生産全体のスピードは上がりません。なので、最も弱い部分(ボトルネック)を特定し、それを解消することが全体の成果を最大化するカギなのです。
つまり、「うまくいっていない原因」を的確に特定し、それを改善することが最短ルートです。
- 仕事ができる「嫌な奴」

工藤 正悟ブリリアントジャーク、トキシックワーカーと呼ばれる有害社員のことです。
本人は優秀だが、協調性がなく周りに悪影響を及ぼす社員のことです。
Netflixが「チームワークを底合うブリリアントジャークに居場所はない」と明言したことで広く周知されました。
アメリカの研究では、組織にブリリアントジャークがいると全体のパフォーマンスが30%~40%低下すると言われています。よって、ブリリアントジャークを解雇した方が組織にとってプラスになるということです。
それは、我が強く自分の意見を押し通すからだそうです。
Googleの採用基準に「グッドネイチャードパーソン」があります。能力よりも根の良さを優先したということです。
- 仕事はアンチエイジング

工藤 正悟高齢者を取り巻く健康面でこれから増加すると言われているのが「フレイル」という状態です。
フレイル:心身が老い衰えた状態。特に身体に関してはフレイルになると更に体を動かさなくなり、よりフレイルを加速させるフレイルサイクルに陥る。
フレイルの予防には栄養、身体活動(運動)、社会参加の3要素があると言われています。
- 労働している高齢者は要介護の割合が70%以下
- その中でも認知症による要介護状態の割合は50%
- あたり前をちょっと変えてみる

江原 智恵子相手に印象を持ってもらうためには、普段、あたり前に行っていることをちょっと変えてみることが大事なのではないでしょうか?
例えば、お客様をお見送りする際、お客様が見えなくなるまで深くお辞儀をしている光景を見ますが、お客様が最後に見る景色が頭頂部でいいのでしょうか?それより、最後はお客様の顔を見て笑顔でお見送りした方が相手に笑顔の印象が伝わるので、又行こうとか又会いたいと思ってもらえるではないでしょうか?
普段あたり前にやっていることに疑問を持って、ちょっとだけ変えてみると印象に残る人になれるのではないでしょうか?
- 心の安心

土肥 宏行私たち人間が大昔から求めていた欲求は「安心感」です。
脳はしなないことを最優先に考えていましたが、現代における安心感は「心の安心」です。ここにいると安心。この人といると安心ということです。
では心が安心することができないとはどういうことなのか?
否定されると人は傷つきます。負の強い感情は心に残りやすいといいます。そうするとその場所や人から距離を置きたくなる。なぜなら人は傷つきたくないから。否定されることが怖いのです。
仕事でもプライベートでも相手に話を聞いてもらうためには、心の安心について気を使ってみる必要があるのかもしれません
- マニュアルがない場合とある場合

中澤 正裕マニュアルがない企業として有名なのがスターバックスです。
ドリンクのレシピにはマニュアルが存在しますが、接客マニュアルは存在しません。働く人が自発的に動き、ホスピタリティの実現を目指しているからです。会社も決して従業員に任せっきりではなく、人事制度、教育制度を整備しています。
次に、マニュアルがある企業の一つにマクドナルドです。
誰がやっても品質を変えずスピーディーに商品を提供する目的で、無理や無駄が取り除かれた細かいマニュアルがあります。
やり方は違いますが目指しているところは、「お客様が何を求めているか」だと思います。
求められることが日々変化する状況ではアップデートが必要です。ルーティン化、マニュアル化された業務で相手は満足するのか考えて仕事をしていきましょう。
- 私はイチゴクリームが大好物だが、魚はミミズが大好物だ。

中澤 正裕だから魚釣りをする場合、自分のことは考えず、魚の好物のことを考える。
料理人は時々、自分の好みや、作りたい料理に固執し過ぎることがある。しかし、本当に大切なのは、客が何を求めているかを理解し、それに応えること。客が求めるのは、美味しい料理だけではなく、快適な空間、心地よいサービス、そして何よりも、自分の要望が理解され、尊重される経験。 客の期待に応える、越えるというのは、どの仕事でも必要なこと。そのためには、常にお客様の声に耳を傾け、改善を続けることが必要
- 検証をしよう。

丹下 優子日本人は“検証”をしない国民性があるそうだ。
コロナ対応のため、世界各国で医療機関に多額の資金が投入されたが、米国ではそれに見合った対策が行われず、病院の口座が潤っただけという結果が出ている。日本はどうかというと、病床や人員を増やすなどの対策が行われたのかどうかのデータ取りすらされておらず、“検証”する材料すらない。湾岸戦争自衛隊派遣の結果はわずか4ページの報告書が提出されただけだそうだ。
何事も始めてみることは重要だが、放りっぱなしにせず、どのような結果であれ2度目3度目に活かせる検証を、忘れないようにしたい。
- やってみるまで結果は分からない。

中瀬 拓哉改正健康増進法の成立により、飲食店には2020年4月から原則屋内禁煙が義務づけられた。飲食店業界では、禁煙すると売上が下がるという声もあったが、いざ全面禁煙してみると売上が上がったケースがある。
大手ファミレスチェーン店では、ただ全面禁煙にしただけでなく、その対策として受動喫煙を望まない客層に配慮した環境を作り、結果ファミリー層の取り込みを行った。その結果禁煙化を実施した月は既存店で客数が減少したが、客単価は増加したことで、売上でみると増加となったそうだ。
当時は客足が減り売上が下がると思われていたことでも、いざ実行してみると思いがけない結果に繋がることもある。
頭で考えることも大事だが、いくら考えても実行しなければ結果は分からないこともあるので、躊躇わず勇気を出して行動していきたい。
- ブランドはお客様が決める

江原 智恵子ブランドとは何かと言えば「他との違い」だと思います。
そしてお客様にその違いが伝わらなければブランドにはなりません。ブランドというと、まず会社名や商品、サービスを思い浮かべますが、これからは自分自身をブランドとしてお客様に認知してもらうことが大事なのではないでしょうか?
その時に、私はこういう人間ですと主張してもダメで、あくまでも「ブランドはお客様が決めること」だと思います。自分自身が信念をもってお客様にとってよいと思うことをすることで、その人自身の個性や価値が生まれ、それが自分自身のブランドとなり、お客様からブランドとして認知してもらえるのではないかと思います。
- この鉛筆を作れる人は世界に一人もいない

土肥 宏行フリードマンという経済学者のスピーチです。
鉛筆一本もって言います。
「この鉛筆を作れる人は世界に一人もいない」
これが作られている木は伐採された木からでき、その木を切り倒すノコギリには鋼が使われ、その鋼には鉄鉱石が必要。黒い芯にはグラファイトが使われている。
何千もの人がかかわってその鉛筆1本が作られたと説明する。同じ言語を話さない人、異なる宗教を信仰する人が協力して作っている。
お金が世界中の人を繋げている。
一人一人が誰かの問題解決をしているから成り立つ。我々一人一人の力がどこかで誰かの役に立っているということです。
- スマホ時代に在り続ける手帳

磯部 優子スマホでスケジュール管理ができるようになった現在ですが手帳の売上が増えているそうです。
最近ではスケジュールを書きこむだけでなく「ライフログ」をつけるという使い方が流行っているそうです。
デジタル時代に「紙の手帳」の売上が伸びていることに驚きですが、手帳が売れ続けている理由として「買い手の使い方」にヒントがありそうです。最近の手帳の使い方を3つ紹介します。
- 推し活手帳として。推しのイベントの予定を書くほか、感想やイラストとともに記録。
- 健康管理のログとして。4段階のマークをつけたり、見返したときに文字の綺麗さで過去の体調を感じ取ることができ振り返りができるとのこと。
- 中には、その日インスタント味噌汁がとてもおいしく感じたというので味噌汁のパッケージを貼っている人も。手帳の厚みが増すのが醍醐味なんだとか。
- 働き方改革による考察

堺 友樹日経新聞の記事によるとフリーランスが会社員に転職する人が増えている。
- コロナや働き方改革によりフリーランスが増加し競争が激化。
- 収入の変動の大きさに加え物価高が影響し安定志向へ。
- 働き方改革により会社員でも柔軟な働き方ができる。
また、大手企業を中心に出戻り社員も増加傾向にあり、働き手不足を少しでも解消したい思惑もある。
これらのメリットは会社と従業員のミスマッチが起きにくいという点であり、仕事で必要なスキルが備わっている可能性が通常の採用より格段に高くなっている。
退職者を社内に戻しいれるなど環境の整備も必要かもしれない。